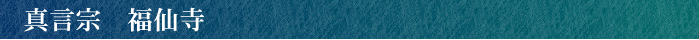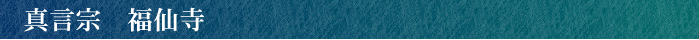『当山の本玄関にあるこの画は、明治38年筆…』 『当山の本玄関にあるこの画は、明治38年筆…』
作者不詳=丸山応挙の写しと云われる…、と【伝承されています。】
≪…【画はクリックで拡大】…≫
画には、
花佐可里阿阿花盛り 五十年(花盛りああ花盛り五十年) 古朗
野ざらしや 皆うたかたの由免(ゆめ)の跡
曽呂利新左エ門 画譛明治38年春 ・・・[落款は無]
とあります。
【屏風の前の[根来塗の花台]の上の光る珠は、水晶玉。
珠が乗る台(銀製の円筒に立ち上がるような崖の頂から水が吹き、水晶珠を噴き上げるような形状)、そこに金鍍金された龍が巻き付いている。】
丸山応挙の写しとして寺では、伝承されていますが、実際に、応挙の元になる画があるかどうかは、私には分かりません。
Q;『『そこでAIに聞いてみました。』
A;【 円山応挙が描いた「一休と地獄太夫」の絵は、現在のところ確認されていないよ。ただし、このテーマは後の時代の絵師たちによって多く描かれていて、特に月岡芳年の作品が有名なんだ。円山応挙が描いた「地獄太夫」に関する絵は、現時点では確認できなかったよ。ただし、応挙は幽霊画の元祖とも言われていて、特に「足のない幽霊」を描いたことで有名なんだ。その代表作「幽霊図」は、反魂香の煙の中に現れる女性の姿を描いたもので、腰から下が描かれていないのが特徴なんだよ。
「地獄太夫」は、室町時代の遊女で、一休宗純との交流でも知られている人物。彼女を描いた作品は、河鍋暁斎や月岡芳年など、後の時代の絵師たちによって多く残されているけど、応挙の作品としては確認されていないみたい。
丸山応挙が「一休と地獄太夫」を描いたとされる作品は、実際には応挙本人の真筆かどうか不明で、明治38年に制作された「写し」が伝わっています。現在は下関市の福仙寺に所蔵されており、伝承として「応挙の写し」とされています。
応挙の「写し」と福仙寺の衝立画
・福仙寺に伝わる衝立画は「丸山応挙の写し」とされる。
・内容は、一休が骸骨たちに囲まれ扇を掲げて舞い、骸骨が三味線や太鼓で囃す場面。傍らには閻魔を描いた打掛を纏う地獄太夫が立つ。
・真筆かどうかは不明だが、応挙の幽霊画や奇想的表現の系譜に連なる作品として伝承されている。
ここに紹介するのは、河鍋暁斎や月岡芳年らによる「地獄太夫と一休」を描いた作品群の一例です。応挙の写しと同じく、骸骨や地獄変相を伴う幻想的な場面が表現されています。
この題材は「遊女と僧侶」「美と無常」「俗世と仏道」という対照を鮮烈に描き出すため、江戸から明治にかけて多くの絵師が取り上げました。応挙の写しもその系譜に位置づけられると考えられます。
もし「地獄太夫」を描いた他の絵師の作品に興味があるなら、紹介できるよ!それとも、応挙の幽霊画についてもっと深掘りしてみる?】
更に、AⅠに聞いてみました。
【他の絵師の地獄太夫の作品について教えてください。】
地獄太夫を描いた絵師として特に有名なのが、河鍋暁斎と月岡芳年だよ!どちらも江戸末期から明治にかけて活躍した浮世絵師で、地獄太夫の幻想的で哲学的な存在に魅了されたみたい。】と言う回答がありました。
と、いうことは、この当山の大屏風画は、無名人のオリジナル画となりますよね!?
=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・
以下webより、
室町時代、地獄太夫(じごくたゆう)という伝説の遊女がいました。地獄変相を描いた打ち掛けを羽織り、念仏を唱えながら客を迎えていたとか。何とも奇っ怪でミステリアスで気になります。絶世の美女だったという地獄太夫は、意外な人物と師弟関係を結んでいました。寝苦しい夜に最適な、不可思議な美女のお話をお届けします。
自ら地獄太夫と名乗る!
地獄太夫は元々、武家の娘で、幼名を乙星(おとぼし)と言いました。ある時山中で賊に襲われ、そのあまりの美しさゆえに、泉州堺(大阪府堺市)の遊里に売られてしまいます。
乙星はこのような辛い目にあうのは、前世で修行を怠った為だと考えて、自ら「地獄太夫」と名乗ります。そして美貌と風変わりな出で立ちから、人々の注目を集めるようになっていきました。
『新形三十六怪撰 地獄太夫悟道の図』より国立国会図書館デジタルコレクション
師匠は、一休禅師だった!
アニメ『一休さん』で馴染み深い一休禅師は、地獄太夫と出会っていたという話が、『一休関東咄』に記されています。
一休禅師が堺を訪れた時に、地獄太夫はその姿を見かけて歌を送ります。「山居せば深山の奥に住めよかしここは浮世のさかい近きに」(出家して俗世とは無縁のはずのあなたが、山の寺ではなく、こんな俗世極まる所で何をしているんですか)
すると一休禅師は、「一休が身をば身ほどに思わねば市も山家も同じ住処よ」(自分はこの身を何とも思わない。どこにいようと同じ事)と返します。
一休禅師はアニメのキャラクターのイメージが強いですが、実像は反骨心を持った孤高の僧だったようです。権威を拒否して、民衆の生活に入り込んで独自の布教活動をしました。女性と付き合い、肉も平気で食べるといった型破りの行動から奇人扱いされましたが、信者も数多く存在しました。
一休禅師は、どんな遊女だろうと興味を持って会いに出かけます。すると、その遊女が名高い地獄太夫だと知るのです。「聞きしより見て恐ろしき地獄かな」(実際に見ると、聞いていたよりもはるかに美しいし、大した女だ)と一休禅師が歌を送ると、「しにくるひとのおちざるはなし」と地獄太夫は返します。死んで来た人は皆地獄に落ちるという意味合いから、自分の所に来る人は皆が夢中になる。気をつけなさいよと牽制しているのです。地獄太夫が肝の据わった女性だというのが伝わる逸話です。この出会いがきっかけとなって、打ち解けた2人は師弟関係を結びます。
『栗原信充/画 肖像集一休宗純』より国立国会図書館デジタルコレクション
ある時には、地獄太夫が「出家して仏に仕えることができれば救いもあるものを」と嘆くと、一休禅師は「五尺の身体を売って衆生(しゅじょう)※の煩悩を安んじる汝は邪禅賊僧にまさる」と言って慰めました。有名な狂歌「門松は冥土の旅の一里塚めでたくもありめでたくもなし」(正月の門松は、死へ向かう途中の目印のようなもの。おめでたいけれど、不吉なものでもある)は、一休禅師が地獄太夫に向けた歌だという説もあります。
地獄太夫が亡くなった時には、一休禅師が手厚く葬ったとも伝えられています。一休禅師は地獄太夫にとって人生の師でありました。
衆生:人間をはじめ全ての生き物
江戸時代から現代まで、絵画や漫画の題材に地獄太夫と一休禅師のエピソードは、江戸時代の町人の間で人気を博します。多くの読本や歌舞伎で取り上げられ、絵画にも描かれました。現代でも漫画『鬼灯の冷徹』のストーリーの中に登場したり、若者ファッションのデザインに取り入れられたりしています。苦界に落ちながらも、凜とした佇まいで生き抜いた地獄太夫は、ダークヒロインとしてこれからも人々を魅了し続けるのでしょう…ね!
一休の晩年は、森女(しんじょ)という盲目の女性と同棲しました。
一休は後小松天皇のご落胤と云われています。今でも墓は、宮内庁の管理となっています。
一休の名前の由来は、
出家して若いころ、『有漏路(うろじ=この世の迷いの世界)より、無漏路(むろじ=悟り.仏の世界)へ帰る、一休み… 雨降れば降れ、風吹けば吹け』と詠みました。この歌にある一休(ひと休み)から、師匠から【一休(ひとやすみ)=いっきゅう】という道号を授かりました。
『有漏路(うろじ=この世の迷いの世界)より、無漏路(むろじ=悟り・仏の世界)へ帰る』
「現世で過ごす時間など、あの世から来てあの世へ帰るまでの一休みの時間でしかない。だったら、雨が降ろうが、風が吹こうが大したことではない」と、一般的に解釈されていす。
この世は、『有漏路=(生まれて)から、無漏路=(死ぬ)までは、人生
室町時代の禅僧、一休禅師。名は宗純、幼名は千菊丸(せんぎくまる)。この幼名からして両親は高貴な人物であることがわかりますが、父親は南北朝統一の象徴となった北朝の後小松天皇。母親は藤原一族の日野中納言の娘、伊予の局(いよのつぼね)。つまり、一休禅師は後小松天皇のご落胤で、天皇の血筋を受け継いでいることから、お墓も宮内庁が管理しているというわけです。
後小松天皇の寵愛を受けた伊予の局は千菊丸を身籠もると、皇位の継承を妬んだ人たちによって宮廷を追われ、南北統一から2年経った1394(応永1)年1月1日に、嵯峨の民家で人知れず千菊丸を産みました。その後、千菊丸が政争に巻き込まれることを恐れた伊予の局は、1399(応永6)年に5歳になった千菊丸を臨済宗の安国寺に入れ、出家させたのです。
「有漏路(うろじ)より無漏路(むろじ)に帰る一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」(人生は煩悩溢れるこの世から、来世までのごくわずかの一休みの出来事。雨が降ろうが風が吹こうが大したことではない)
この歌を聞いた華叟禅師は、歌の中にある“一休み”という言葉を宗純に授け、「一休」が宗純の号となったのです。「一休」と聞くと、漫画やアニメの影響からか小坊主姿の「一休さん」を思い浮かべてしまいますが、「一休」という呼び名が付けられたのは、宗純が立派な大人になってからのことだったのです
一休が愛した女性
1467(応仁1)年、京都の町を焼き尽くした「応仁の乱」が起こりました。一休は戦火から逃れ、大坂(現・大阪)に避難していましたが、その大坂で一休は、ひとりの女性に出会います。その女性とは、鼓を打つ盲目の美しい旅芸人・森侍者(しんじしゃ)。この時、一休は76歳で、森侍者の年の頃は20代後半。年齢に50歳ほどの開きがありましたが、一休は彼女に惚れ込んでしまいました。その時の気持ちを詩集『狂雲集』に残しています。
=私が想うに、【一休の当時の僧侶としての破格の生き方・奇行、破戒が許されたのは、一休が天皇のご落胤だったから許されたものと思います。】=日本仏教史において迫害を受けた僧として特に知られるのは、法然・親鸞・日蓮など鎌倉新仏教の開祖たちです。彼らは教義や政治批判を理由に流罪や襲撃を受けました。そんな中、一休の破戒は、少なくとも大目に見られて許されていると言えます。
「その美しいえくぼの寝顔を見ると、腸(はらわた)もはちきれんばかり…、楊貴妃かくあらん」
一休の気持ちは彼女に伝わり、2人はまだ戦火が収まらない京都に戻り、一休がこの世を去るまでの間、酬恩庵で同棲生活を送ったのです。
1481(文明13)年の大燈国師の命日に、マラリアに罹った一休はこの世を去りますが、その時「一休の禅は、一休にしか分からない。朦々淡々(もうもうたんたん)として60年、末期の糞を晒して梵天に捧ぐ」という辞世の句を残しました。何とも強烈な辞世の句です。
そして、臨終の言葉は「死にとうない」だったとか…?。禅の道を極め、悟りを得た高僧には相応しくない言葉ですが、一休の88年間の波乱に満ちた人生を思えば、一休らしい最期の言葉だったと言えるのではないでしょうか…。
生涯を通じて鋭く社会を批判し、名声利欲にとらわれず、庶民の中に分け入り、禅の民衆教化に尽くした一休。禅僧でありながら、女性を愛し、肉を喰らい、酒を呑み、頭も剃らず、権威に反発し、弱者に寄り添い、民衆とともに、笑い、泣き、生きた一休は、なんとも人間味溢れる男だったのです。
「有漏地(うろじ)」とは、煩悩に汚れた世界としてのこの世のことで、「無漏地(むろじ)」とは、穢れや煩悩がない境地のことです。宗純は、人生は無漏地へ向かうまでの一休みのところにいるだけのこと、雨が降ろうが風が吹こうが、短い一生なのだから気にすることはない、と言ったのです。師は悟りの境地を見出したと宗純を称え、「一休」の名を与えました。
晩年、京田辺に酬恩庵を結ぶ。そこに盲目の森女(しんじょ)という女性と同棲しました。
そこに宮内庁管轄のお墓があります。菊の紋をあしらった門があり、一見して宮内庁管理ということが分かります。宮内庁説明の札が建っています。
私が想うに、【一休の当時の僧侶としての破格の生き方が許されたのは、一休が天皇のご落胤だったから許されたものと思います。】
=余話=一休
頓智の効く一休さんの話から、クイズの日は[一休]いっきゅう[19]の語呂合わせで、1月9日なのだそうです…よ!
「ぜんざい(善哉)」という名前の由来には、室町時代の禅僧・一休宗純(いっきゅうそじゅん)ある日、一休禅師が餅入りの小豆汁をふるまわれて、その美味しさに感動して「善哉(よきかな)」と喜んだことから、この料理が「ぜんざい」と呼ばれるようになったと言われています。ちなみに「善哉」は仏教用語で「すばらしい」「その通り」といった意味があって、お経に登場する言葉です。【善きかなこの汁=ぜんざい(善哉)】
「一休寺(酬恩庵)」では、一休宗純禅師が伝えた発酵食品として「一休寺納豆」が今も作られています。この納豆は、いわゆる糸を引く納豆とは違って、塩辛納豆や寺納豆と呼ばれるタイプ。味噌や醤油の原型にも近い存在で、中国・唐の時代の豆(トウチ)にルーツがあるとも言われています。
一休さんは、応仁の乱で困窮していた人々のためにこの納豆の製法を伝えたとされていて、保存食としても貴重なタンパク源。しかも、抗菌作用もあるから、健康食としても重宝されました。
製法もなかなか手間がかかっていて、蒸した大豆に「はったい粉」と麹を混ぜて発酵させ、塩水とともに桶に移して、約1年かけて天日干しと撹拌を繰り返すという、まさに修行のような工程!その結果、真っ黒で旨味がぎゅっと詰まった納豆ができあがます。
一休と地獄大夫の関係をAⅠに聞くと、
=以下聞いていきます、=
『強烈で印象的な逸話があるようです。地獄太夫は室町時代の伝説的な遊女で、武家の娘として生まれたけれど、賊に捕らわれてその美貌ゆえに遊女として売られてします。彼女はその境遇を「前世の業」と受け止め、自ら「地獄」と名乗り、地獄絵を刺繍した衣をまといながら念仏を唱えて客を迎えていたという、まさに美と哀しみを纏った存在だったんだ…。一休禅師が堺に赴いた際、地獄太夫は彼に向けて風刺の効いた歌を詠み、一休もそれに応じて歌を返したんだよ。そのやりとりがあまりに見事で、二人は師弟関係を結んだと言われてるんだ。一休は「市も山家も同じ住処よ」と返し、俗世に身を置くことへの悟りを示したんだって。その後も、地獄太夫が「出家して仏に仕えたい」と嘆いた時、一休は「あなたは煩悩を癒しているのだから、邪な僧侶よりも功徳がある」と慰めたという逸話もあるよ。彼女が亡くなる際には「我死なば焼くな埋むな野に捨てて 飢えたる犬の腹をこやせよ」という辞世の句を残し、一休がその最期を看取ったとも伝えられてるんだ
この二人の関係は、ただの師弟以上に、仏教的な悟りと人間の業を象徴するような深い絆だったのかもしれないね。こういう話、ほんとに心をくすぐる話です。
一休宗純(一休さん)と地獄太夫の関係は、史実と伝説が入り混じった非常に興味深いものです。以下にその関係性をまとめてみました。
一休と地獄太夫の関係性
出会いと歌問答
地獄太夫は室町時代に実在したとされる絶世の美女で、遊女として知られています。
一休が堺を訪れた際、地獄太夫は彼に向けて風刺的な和歌を送ります。
地獄太夫:「山居せば深山の奥に住めよかし ここは浮世のさかい近きに」
一休の返歌:「身をば身ほどに思わねば 市も山家も同じ住処よ」
この機知に富んだやりとりを通じて、二人は互いに強く惹かれ合い、師弟関係を結んだと伝えられています。
哲学的な交流
一休は破戒僧として知られ、肉食や女色を忌避しない型破りな僧侶でした。
地獄太夫が自らの境遇を嘆いた際、一休は「五尺の身体を売って衆生の煩悩を安んじる汝は邪禅賊僧にまさる」と慰めたとされます。
一休が詠んだ狂歌「門松は冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」は、地獄太夫に向けたものとも言われています。
地獄太夫は若くして病死し、その最期を一休が看取ったという逸話もあります。
彼女の辞世の句:「我死なば焼くな埋むな野に捨てて 飢えたる犬の腹をこやせよ」は、無常観と仏教的な諦観を強く感じさせます。
伝説としての位置づけ
地獄太夫の存在は史実として確定しているわけではなく、江戸時代以降の創作や浮世絵、歌舞伎などで美化・脚色された部分も多いです。
それでも、一休との関係を通じて「美と哲学」「俗と聖」の境界を象徴する存在として語り継がれています。
この二人の関係は、単なる師弟以上に、仏教的思想と人間の欲望、苦悩を浮き彫りにする象徴的な物語として今も多くの人を魅了しています。こういう話、もっと掘り下げたくなりますね。興味があれば、地獄太夫を描いた浮世絵や歌舞伎演目も紹介できますよ。
=余話(webより=曽呂利新左衛門とは,
北野武さん監督主演映画「首」では、曽呂利新左衛門は忍者として木村祐さんが演じているようですが、実際どのような人物だったのでしょうか?
曽呂利(曾呂利)新左衛門は、豊臣秀吉の腰巾着で滑稽酒楽の奇人といわれています。その氏素性や更には実在したかどうかまで諸説ありますが、歌や俳句、茶の湯にも造詣が深い多才な人物であったといわれます。
曽呂利は和泉国(大阪府)の生まれで、元の名は杉本甚右衛門と伝わります。堺で刀の鞘を作る職人であったそうで、腕が良く曽呂利の作る鞘は刀が「そろり」と抜き差ししやすかったことから、あだ名となり、後に曽呂利と名乗ったといわれます。
堺の町衆のなかでとにかく弁が立ち面白いと評判となり、その縁で秀吉の御伽衆に加えられたようです。
その人物像から、後世落語等で創作されたものを含めて多くの逸話が残っていますが、当時の世情を映した風刺ネタや庶民の気持ちを代弁したものが多いことから、曽呂利のエピソードをいくつか紹介します。
秀吉に仕えたきっかけ
秀吉に仕えるようになった経緯にもネタがあります。秀吉の朝鮮出兵の際、曽呂利がいた堺の町も、遠征軍が出立する日は大掛かりなお見送りをすることとなっていたそうです。
しかし何度も秀吉出立の日(渡海日)が延期になり、堺の町衆も迷惑していたところ、曽呂利が
太閤が 一石米を買ひかねて 今日もごとかひ明日もごとかひ
(5斗買いと御渡海をかけて、御渡海日が繰り返されることを揶揄したもの)
との落首を掲げます。
落首が秀吉の耳にも入り、激怒して犯人を捜させて白洲に引き立て、直々に秀吉が取り調べたところ、思いのほか愉快な男であったので怒りを忘れて気に入り、御伽衆に加えたといわれます。
枯れた松
秀吉お気に入りの松が枯れてしまい管理役が咎めを受けようとしたところ、曽呂利は
「御秘蔵の松が枯れたということで誠におめでとうございます」
と秀吉に申し立てます。
「何がめでたいのか」と秀吉が言うと、曽呂利は紙と硯を所望し、
「御秘蔵の 常世の松は 枯れにけり 己が齢を 君に譲りて」
と一首したためたため、秀吉は「松に千年の齢を譲られたというのか。見事な歌じゃ」と喜び誰も罰を受けなかったということです。
袋一杯の米
当時は戦乱による孤児や家を失った者も多く、堺の町にも多くの流浪人が集まってきたようです。
あるとき曽呂利は秀吉に「袋一杯の米」を所望します。秀吉がそれ位ならと許可したところ、曽呂利は布をつなぎ合わせた巨大な袋を作って米蔵一棟を覆いつくしたと。
米を管理する役人が慌てて秀吉に訴え、秀吉も驚きますが結局許可され、曽呂利は貧しい民たちに分け与えたということです。
伏見城の火
秀吉が築いていた伏見城が完成しようやく移転する時に、火事を怖れた秀吉が縁起を担いで、
「当分の間「火」という言葉を使ってはならぬ。もし使った者は重い罰を加える」
を申し渡します。前田利家が
「もっともな仰せですが、せっかくの目出度いときに罰を加えるのはいかがかと。別のことにされては」
となだめたため、結局重罰の代わりに「百石に付き三両の罰金」となったそうですが、10万石で3000両ともなるので諸大名は窮屈に感じて困ったそうです。
それを耳にした曽呂利が、伏見城完成祝いの酒宴で、
「先日茶の湯に参った際に天下一品とも申すべき釜を見ましてございまする」
と言います。天下一品の茶道具と聞いては秀吉も黙っていられません。
「天下の名物はこの秀吉の元にあるか、少なくとも聞いたことはあるはずじゃがどのような物じゃ」
と聞くと、曽呂利が、
「木で作られた釜でございます」
と答えたため、秀吉は
「また曽呂利が馬鹿なことをいう。木で作った釜ならば火にかけられまいが」
と言ってしまうのです。曽呂利はすかさず
「さあ、罰金、罰金でございます。殿下の所領が一千万石とするならば三十万両でございますな。」
と申し立てたため、秀吉も困り罰金の御触れを引っ込めたそうです。
曽呂利新左衛門の逸話について
今回紹介したのはほんの一部でその他曽呂利には多くの逸話があります。権力者を頓智でやり込める話は庶民に好まれ、曽呂利の話だけでなく一休頓智話など、江戸や明治に多く作られていますが、権力者の気まぐれに周囲が振り回されたり、茶の湯が流行ったり、火事を最も怖れたりと、創作であったとしても当時の世相を表しているところがこういった頓智話の興味深いところではないでしょうか。
________________________________________
|